働き者の地底人に会った
2002年9月17、18日 西表島・ヒナイ川河口 |
南西諸島の干潟に棲む「ミナミコメツキガニ」です。 じつは、西表島に来るにあたって私がいちばん会うのを楽しみにしていた生き物は、イリオモテヤマネコでもカンムリワシでもなく、このカニでした。昔テレビの自然番組で見てから、ず〜っと気になっていたのです。 ようやく巡り会えたミナミコメツキガニを観察しました。 |
 |
 |
| この生き物はどうもカニらしくありません。なぜかというと、まず体の形がカニのように平べったくありません。ロボットのようにも、正体不明の宇宙人のようにも見えます。そしてなんと、カニのように横に歩かず、前に歩くのです。それも、大勢集まって大行進するのです。 砂の中から現われ砂の中に消えるので、私は地底人と呼んでいます。 |
|
 |
 |
| 人が近づくとたちまち砂に潜って隠れてしまうので、その存在に気づかない人もいるのですが、西表島の干潟にはおびただしい数が棲んでいます。潮が引きつつあるとき遠くの水際をよく見ると、このカニがたくさん集まって行進しているのを見つけることができます。観察には双眼鏡があると便利です。上の写真ではたいした数ではありませんが、潮の引き加減がよいと、もっともっとたくさんの行進を見ることができます。このような習性があることから、「軍隊ガニ」とも呼ばれているそうです。 こうして水際を移動しながら、両方のはさみで砂を口に運び、有機物、すなわち微小な生物や生物の死骸が細かくなったものを濾しとって食べているのです。 |
|
 |
 |
| ↑ 潜っているところ | ↑ 潜った後 |
| 危険を感じると、いっせいに砂に潜って隠れます。片側の脚で砂を掘りながら反対側の脚で後ずさりするように身体を回転させて、砂に身体をねじ込むようにして隠れます。隠れ終わるまでほんの1、2秒です。 上左の写真は砂に潜っているところ、上右は隠れ終わったところです。どうです? 分からないでしょ。みごとな早業です。 |
|
 |
 |
| ↑ 大慌て | ↑ 粗忽者 |
| でも、たまには間違いもあります。上左の写真は、川の縁(へり)の砂に隠れようとしたのに川底が硬くて潜れなかったので、「ヒャ〜!」という感じで逃げ惑っているところです。大慌てぶりが愉快でした。
いっぽう上右の写真のカニは、うまく隠れたつもりらしいのですが、外から丸見えです。この世界にもオッチョコチョイはいるんですね。でもそのおかげで、どんな姿勢で砂の中に隠れているのかが分かりました。眼が出るか出ないかの状態で潜んでいるんですね。 |
|
 |
← 隠れたカニは、外が安全になったなと感じると砂の中から出てきます。姿勢を低くしてじっとしていると、出てくるのを見ることができます。約30秒を過ぎたあたりから、気の早いのが様子を見に現われます。そのままじっと我慢を続けていれば、1分もするとほとんどが出てきて、摂食を始めます。 気がつくと私の周囲がこのカニでいっぱいになり、彼らがせっせと食事をする音が聞こえました。このカニのファンとしてはとても幸せな瞬間です。 |
| 潮が引ききってしまうと、このカニは外では採食をしません。餌を濾しとるにはある程度の水分が必要なようです。ですから、干潟でこのカニを見かけなくなります。砂の中に潜ってしまうのです。でも決して休んでいるわけではありません。潮が引いてから時間が経った砂の上に右の写真のような模様ができているのを見つけることができます。このカニが砂の中でもせっせと働いた証拠です。 |  |
 |
 |
| ↑ 14時00分 | ↑ 14時06分 |
| 潮が引いて間もない干潟に上左のようなものを見つけました。小さな砂団子の集まりです。見ていると、砂団子がひとつずつ増えていきます。カニが砂の穴の中にいて、食べ終わった(濾過し終わった)砂団子を外に押し出しているのです。 椅子代わりの発泡スチロールの浮きに腰を降ろしてじっくり見ていると、わずか6分ほどで上右の写真の数まで増えました。砂団子を押し出すとき、このカニの脚がちらりちらりと見えます。
|
|
 |
← そのうち、近くの同じような場所から、数匹のカニが地上に出てきました。「あー疲れた!」と休憩しているように見えます。私も一息ついてあたりを見回すと、初めは何もなかった干潟の砂一面に、砂団子の模様ができていました。驚くばかりの働きぶりです。
|
 |
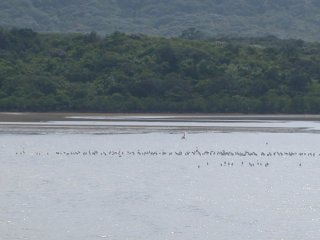 |
| 砂の上に鳥の足跡がありました(左の写真)。砂をつついたり、カニをくわえ直したらしい跡もついています。白い円は100円玉です。ダイシャクシギがたくさん来ていましたから、それがミナミコメツキガニを食べた跡でしょうか。コサギやダイサギも来ていました。右の写真は、潮が満ちてきた干潟に集まっているダイサギ(たぶん)です。 上流の森から流れてくる有機物をミナミコメツキガニが濾しとって食べ、そのカニを鳥が食べて最終的には栄養分を森へ還す。干潟の食物連鎖の一端、いや、かなりの部分をこのカニが担っているのですね。 |
|
| ようやく巡り会えたミナミコメツキガニは、思っていた以上に働き者で愉快な生き物でした。その感情が見える気がするのも、この生き物がカニ離れしていると思う点です。もしかして本当に地底人なのかもしれないという気さえしてくるのです。
旅先で1種類の生き物だけをじっくり観察するということはあまりしないと思いますが、よく見れば見るほどその生き物が分かり親しみが持てます。私の場合、今では西表島と聞いただけで、この働き者の地底人の姿が浮かびます。まるでこの島に友人ができたようです。 |
[実践/応用編へ戻る]